希望のかなた
11/12/17 映画
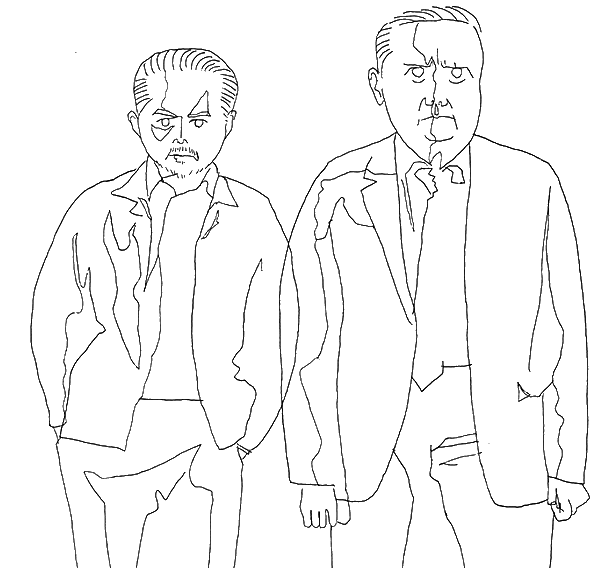
われわれ日本人、いや少なくとも僕は難民問題というとどこか対岸の火事のような気がして親身になって考えた経験がない。
アキ・カウリスマキの難民三部作の一つ「希望のかなた」を観に渋谷のユーロスペースへ出かけた。
内戦が激化するシリアから脱出してフィンランドにたどり着いた若者カーリドが物語の主人公。彼の希望は生き別れた妹を探し出してフィンランドで暮らすこと、だが官僚的なシステムに阻まれて難民申請をパスすることもままならない。街を歩くだけで差別主義者から激しい暴行をうけ、次第に疲れ果ててゆく。一方同じ頃、妻と別れ、人生の再出発をしようとする老紳士・ヴィクストロムはカジノで稼いだ金を元手にレストランの経営にチャレンジする。二人は同時進行で物語を歩み、ある日、ヴィクストロムはレスランのゴミ捨て場で寝泊りしていたカーリドと出会い、救いの手を差し伸べる。「レストランで働いてみるか?」「Yes very much.」こんな感じの緩い会話から心の交流が始まった。
アキ・カウリスマキの作品ではよく不味そうなレストランがでてくる。、今作でも壁になぜかジミ・ヘンのポスターが飾られていていい味をだしている。陰影の強いセットに無表情な役者が加われば、いつのまにかカウリスマキ節の哀愁ただよう世界観が誕生する。一体どこを探せばこんな雰囲気のある役者が見つかるのだろうか。特にヴィクストロム役のサカリ・クオスマネンは映画界の宝だ。一見ちょっと怖そうなのだが実はすごく優しかったりして、そこがたまらなくいい。
カウリスマキは「私がこの映画で目指したのは、難民のことを哀れな犠牲者か、さもなければ社会に侵入しては仕事や妻や家や車をかすめ取る、ずうずうしい経済移民だと決めつけるヨーロッパの風潮を打ち砕くことです」とコメントしている。
作品は昨今の右傾化する世界情勢への危機感から誕生したものだろうが、監督の手法はこれをユーモラスな寓話に仕立て、政治的主張をスパイスで練り込んでいるものだ。だから僕は身構えることなく映画を楽しんだ。同時に、もし自分が難民になったら?あるいは、もし難民を受け入れる立場だったらどうだろうか?と疑似体験する機会も得られた。
物語の終盤、念願の妹との再会を果たしたのも束の間、カーリドはネオナチの暴行に倒れ、苦い結末を迎える。しかし、それでもなお希望を失わなかった。是非、彼の瞳を見て欲しい。明るい未来を見つめている瞳に、この映画の一番伝えたかったことが映っている。そんな気がした。