レディ・バード
03/06/18 映画
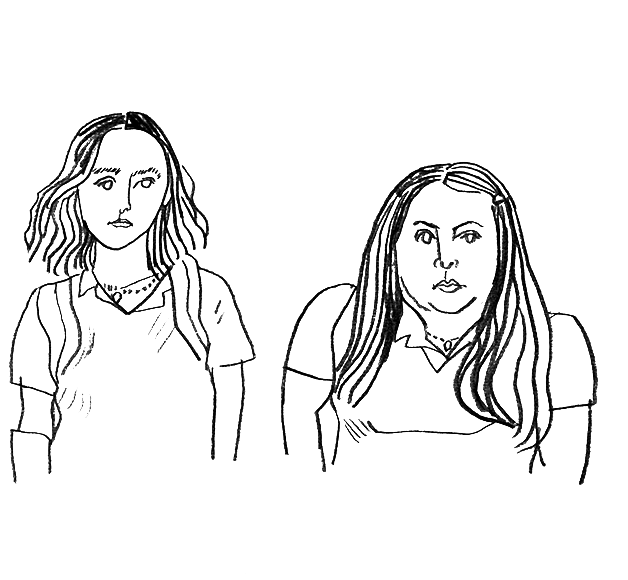
脚本家で女優としても活躍するクレタ・ガーウィックが自分自身の高校時代のことを映画化した作品「レディ・バード」を日比谷シャンテに見に行った。
冒頭こんな言葉から始まる。
Anybody who talks about California hedonism has never spent a Christmas in Sacramento.
(カリフォルニアの快楽主義について語る人は誰も皆サクラメントのクリスマスを経験したことがない。)
サクラメントがどれほどの田舎なのかイメージが沸かないけど、僕は自分が15年間住んでいた拝島に当てはめて考えてみた。都会じゃないし、かと言って絵になるような田舎じゃない。
クリスティーン(シアーシャ・ローナン)はサクラメントにあるカトリック系高校に通う多感な17歳。ダサい街から出てニューヨークの大学へ進学することを夢見る。ところが「絶対に行かせないわよ。地元の州立大学へ行きなさい。」と母親のマリオン(ローリー・メトカーフ)は頑として譲らない。
ここじゃない別の世界にステップアップしたい娘と、現実をわかってもらいたい母のぶつかり合いは、ユーモアを交えてテンポよく進む。母娘はいつも地元のスーパーでいっしょに洋服を買うんだけど、試着中のクリスティンに向かって「お母さんはあなたにベストな状況でいてもらいたいのよ。」とふと漏らした母の気持ちには目も潤む思いだ。それから何らかの理由でお父さんが失業したときにも「お金は人生の成績表じゃないのよ」と言っていたのもこのお母さんだから言えることだ。
すったもんだの挙げ句、娘がNYの大学へ合格して引っ越しすることになった当日、空港ロビーまで見送りに行かず、やせ我慢をしてうろたえた母の演技に許されるならアカデミー助演女優賞をあげたい。
「愛情とは注意を払って見ることよ。」
カトリック高校のシスターが言っていた。
この映画は平凡なサクラメントの街が、注意深く描かれていて、平凡だけど愛情深い作品でした。
飲みすぎて酔いつぶれたクリスティーンが朝方のNYからお母さんに電話をするところで物語が終わる。
終わり方もすばらしい。