20センチュリーウーマン
22/06/17 映画

アネット・ベニング演じるドロシアは大恐慌時代に生まれ、ハンフリー・ボガードとジャズを愛し、四十代で息子を出産。振り返ればその人生は波乱に富んだ20世紀とともにあった。
三四半世紀におよぶ彼女の人生のなかでも今回カメラは1979年のひと夏に焦点を絞っている。
一人息子のジェイミーは15歳、難しいお年頃の子を持つ親というものはいろいろと気苦労が絶えないものだろう。ましてや母子家庭の一人息子というのは特別なものがある。ドロシアは息子をしっかりと自立した分別のある大人の男性に育てるために知恵を絞って、身近にいる二人の個性的な女性に息子の指導を任せるようになる。はっきり言ってこの指導法はどうかしていると思うのは僕だけではないだろう。だいたいお察しの通り、これがかなり刺激の強い人生勉強となってゆくのだ。
物語の舞台はカリフォルニア州のサンタバーバラで、世代的にも何となく懐かしさのようなものがある。
あの頃流行っていたものとか、今よりも良かったこととかが思い出される。
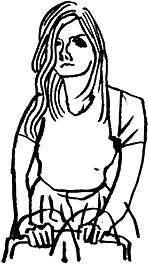
この映画を観ながら、僕は本筋とはあまり関係のないことを考えてしまった。
60年代ころからのカウンターカルチャーがそもそもの始まりだったのかなと思ったのだ。
”強いアメリカ”の時代が終わった。
「本当に心が満たされる自由と幸福はどこにあるのだろう。」-若者たちは権力へ反抗し、アンチ主流の文化を生み出した。
ケルアックやサリンジャー、ボブディラン、後のスティーブ・ジョブズのようなまったく新しいカリスマが登場する土台となり、言うまでもなくそれらは日本にも飛び火して、アートやカルチャーや思想を大きく動かした。
負の遺産としては、例えば地下に潜ったムーブメントからオウム真理教というカルト教団が生まれて、90年代に入ってマグマが噴出したのは記憶に新しい。
その流れも下火になってきたかに思えるが、僕が見てきたものや触発されたカルチャーの源流はここにあったのではないだろうかと、今2017年のこのポイントに立って思った。